2016/06/01 00:00 | 米国 | コメント(6)
ウォルター・ラッセル・ミード 『Special Providence』③
「ウォルター・ラッセル・ミード 『Special Providence』②」の続きです。
前回は、ジェファーソン、ハミルトン、ジャクソンまでを説明しました。
●ウィルソン
最後に残ったウィルソン主義ですが、これは分かりやすいというか、皆さんご存じと思います。
簡単に述べると、ウッドロー・ウィルソンは第一次大戦当時の大統領で、もともとは政治学者です。国際連盟の創設に尽くしたように、人権・民主主義という普遍的価値の追求を重視したことで知られ、現在の米国の価値観外交の象徴的存在として見られています。
ウィルソンがリベラル的価値観の強い民主党員で国際政治学者だったように、この外交路線のキーワードは、民主党、リベラル的価値観、知識人です。
これに対し、共和党といえば、孤立主義あるいは反知性主義的積極外交がイメージされますが、共和党員が価値観に根ざした知性主義的積極外交になることはないかといえば、あります。それがジョージ・W・ブッシュの時代に一世を風靡した「ネオコン」です。
ネオコンについては『米大統領選:第3回共和党テレビ討論会』のコメント欄で説明しましたが、元々のイメージは、民主党員だった知識人・テクノクラートタイプだったが、レーガン時代に転向し、共和党政権の支持者となった人たちです。
この人たちの特徴は、高い学歴と実務経験を有するインテリで、人権と民主主義に強いイデオロギー的こだわりをもっていることです。彼らはカーター政権に代表される民主党の弱腰外交に絶望し、そのために共和党政権(レーガン、ジョージ・W・ブッシュ)に参加するに至りました。伝統的な共和党員(反知性主義、孤立主義、リバタリアン)のイメージからは遠く、新しいタイプの保守主義者ということで、ネオ・コンサーバティブと呼ばれました。
英語の「ネオ」には「ニュー」と違って侮蔑的な響きがあります。伝統的保守主義者は、こういった人たちを、「新参者」で「コウモリ」のような連中だということで、「ネオコン」と呼んだのです(ネオコンのカテゴリーに入る人たちが「ネオコン」と自称することはありません)。
ということで、本書は、4つの類型の思想潮流を提示しています。私がこの本を02年に読んだときは、思想、歴史、外交の連結がとても新鮮で、なるほどなあと思ったものですが、最近はこの枠組みがすっかり定着し、ちょっと古くさくなってきたようです。
たとえば最近では、ユーラシア・グループのイアン・ブレマーが『スーパーパワー ―Gゼロ時代のアメリカの選択』という著作を出しました。
この本は、超大国アメリカの外交の選択肢は以下の3つであるとしています。
① 「Indispensable America」(米国の価値観を世界に広め、世界から必要とされる米国)
② 「Moneyball America」(映画化したノンフィクション『マネーボール』のように、合理的な計算に基づき利益の最大化を追求する米国)
③ 「Independent America」(グローバルな問題に対して直接踏み込むリスクを避け、間接的にコントロールする米国)
ブレマーは、米国民は①②を支持しないので、米国は③の道を選ぶことになると結論づけています。ウォルター・ラッセル・ミードの議論とは、かたや歴史、かたや政策を述べている点でまったく同列には扱えませんが、何か通じるものを感じさせます。
①はウィルソン主義、②はハミルトン主義、③はジェファーソン主義とジャクソン主義に対応するように思われます。しかし、ブレマーの分類の方がずっと直感的でラフな感じがします。
ブレマーはビジネスマン向けに分かりやすい分析を提供するのが得意な人です。歴史とか思想という小難しい部分はあえて突っ込まず、素人でもなるほどと思えるような形に整理したのでしょう。
最後に付け加えると、「ウォルター・ラッセル・ミード 『Special Providence』①」で言及した「アメリカ例外主義(American Exceptionalism)」は米国の歴史を理解する上で重要な概念です。
アメリカ例外主義という思想は、マサチューセッツ植民地を築いたジョン・ウィンスロップの「A city upon a hill」(米国は「丘の上の町」として世界に範を示すべきという考え)に始まると言われます。建国以来の米国と宗教の強い結びつきを背景とした考え方であり、ルイス・ハーツ、リチャード・ホフスタッター(『アメリカの反知性主義』の著者)、ダニエル・ブアステインといった歴史学の泰斗(classical historian)は皆この思想を強く意識しています。
本書の著者ミードも、「アメリカ例外主義」論者の現代版という趣があります。そのことを示す著書の一つが『神と黄金』です。
当社に無断で複製または転送することは、著作権の侵害にあたります。民法の損害賠償責任に問われ、著作権法第119条により罰せられますのでご注意ください。
6 comments on “ウォルター・ラッセル・ミード 『Special Providence』③”
コメントを書く
いただいたコメントは、チェックしたのち公開されますので、すぐには表示されません。
ご了承のうえ、ご利用ください。
![The Gucci Post [世界情勢・政治・経済金融 × プロフェッショナル]](https://guccipost.co.jp/blog/jd/wp-content/themes/gucci_blog/images/etc/head_logo_20220126.png)






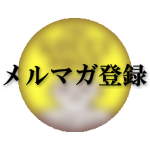




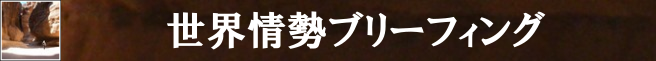

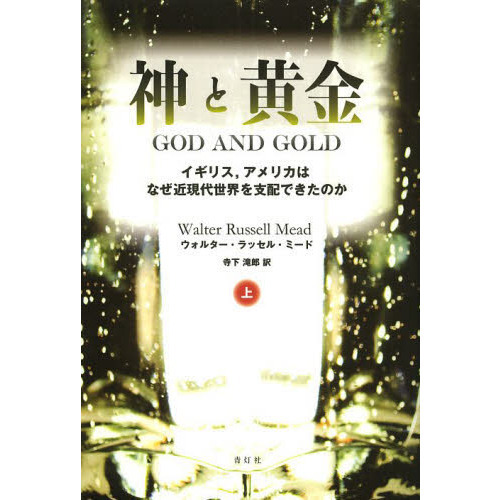


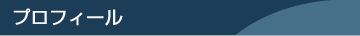



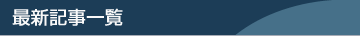

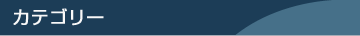
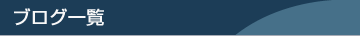






ネオコンの経緯解りやすかったです。イラク戦争後すっかりなりをひそめていますが、カーターにだぶるオバマの反動で復活するのかと思いきや、影も形も見えてこない。ブレマーの分析通りか。父ブッシュはイラン・シーア派とのバランスを考えあえてフセインを潰さなかった。それに不満だったのか解りませんが、ネオコンと子ブッシュのフセイン殲滅をJDさんはどう評価してますか。ネオコンの価値観がシーア派対スンニ派の抗争を軽視しし過ぎたのか。米英は明らかに何かの好機と見たと思いますが、やはり石油のドル取引が主因なのでしょうか。しかしこの戦争で、イランがアフマディネジャトとは裏腹に対米軟化の兆しを見せたのはこの時からだと思うのですが(米国に相手にしてもらいたい北朝鮮と似ている)。現在のシリア難民、イランとの妥協、石油価格につながる複雑な伏線ですね。
アメリカのウッドロー・ウィルソン大統領は新生ソ連に対して「素晴らしい民主主義国家が誕生した」と賛美した。ウィルソンといえばパリ講和会議(1919年)で日本が提案した人種的差別撤廃提案に対して、唐突に「全会一致が望ましい」と言い出し、国際連盟の議長権限で否決した人物。
ウィルソンの周囲を固めていた側近たちは皆社会主義者であった。
ウィルソンとは、こんな人物だったんですねえ。
ところで、大統領補佐官という議会の承認を必要としない、いわば令外官(りょうげのかん)がアメリカ大統領に最も影響を与える地位に就くことができる。キッシンジャー、ブレジンスキー….。アメリカのこの伝統について解説して下さい。
ヒラリーとパネッタが辞めた2期目のオバマは、警察官辞めた割には、ウクライナ介入に関しヌーランドらのオバマの師匠筋のブレジンスキー勢力に好きにさせたと思う。彼らは東欧移民なので対露強硬派でシカゴ周辺が多いが、実際稚拙なやりかたでプーチンの方がまともに見えてしまう。性急なヌーランドはメルケルをこきおろしていたが焦っていた。そうこうするうちシリアで優柔不断な行いで膨大な難民を出すがままだったが、これもCIAにお任せだったのだろう。たしかに子ブッシュまでの米国とは様変わりだ。対中外交でもスーザンライスと組んで中国から軽く見られている。実効力のない価値観外交はウイルソン譲りで似ている。
ウイルソンはFRBの創設を許し、国家を売り渡してしまったと後悔していたというが、以後これを覆そうとするとケネディー兄弟のようになる。このドル紙幣国際金融資本と産軍複合体が米国の権力だが、どうしても世界大戦をやりたかったF・ルーズベルトが起点か。今はこの路線変更の時代かもしれないが、ブレマーを追いかけると共に、F・フクヤマあたりも解説して欲しいですね。
ミードはこんな本も書いてるんですね。これから探して読みます。英国から始めてますが、ピューリタンは近代国家の前提としての絶対王政とすでに対立して、植民ではなく米国へ移民している。王も処刑している。フランスのような場当たり的革命とは違う。仏語のノルマン王朝に征服され下層階級の英語の民として早くから統一的封建国家の下、そういう階級が育まれていたのでは。英仏戦争、ばら戦争、無敵艦隊戦などでさんざん鍛えられ、海賊・海洋・進取の気質もあったのだろう。この気質に合ったプロテスタントとして英国国教会というカトリックもどきと対立したが、米国でも国家植民者と移民との意識の違いが4大潮流にも現れているかもしれない。国家に頼りたくない共和党系か。彼らの神とはお題目ではなく共同体での実践活動で示されるものなのだろう。卒業して国家に移譲されるものでもない。
独立後は封建制度なしからの出発だったため、近代国家の建設でローマの共和政の手本も取り入れ易かっただろう。そして英国の連合王国とはちがう連邦国家となった。ビスマルクからみれば田舎者の反知性的開拓者国家が外交をやっていると揶揄したくなるのだろうが、ドイツなど及びもつかない現代のローマ帝国となった。別にそんなに先が読めているわけではないが、ローマのように時点ごとに反知性的な実益的な判断ができるのだろう。やはりアングロサクソンの伝統か。だから入植者が既にアメリカ例外主義を意識していたのが楽天的ですごい。エンタープライズだ。ただ連合王国も連邦国家も、ユダヤのマネー使いと協働しないとここまで来れなかったのでは。それが黄金の意味なのかな。結局ドイツは絶対王政にも至れず、封建的体質が抜けず、マネー使いのユダヤを人身御供にして自ら崩壊した。それも羊頭狗肉の神聖ローマ帝国と名乗った報いか。ビスマルクこそ米国からその後進性を揶揄されるべきだった(笑)。
どっちの著者のも県立図書館はおろか、岩手大学の図書館にもない。
あまり欧米に縁のない県だからしゃあないかなあ。
岩手大学近くのマクドナルドなんか、夜は中国語が飛び交ってるからアジアからの留学生は多そうだけど。
だけど、イアン・ブレマーさんの本の帯キャッチフレーズが、今のアメリカの気分を端的に表してますね。
めちゃくちゃ面白かったです。私の理解力の問題はさておき、アメリカ人の
全体として現れてくる決定の背景が、なんとなくわかってきました。
サウジアラビアとは一方で手を組み、一方では追い込むという思考もこの本で
個人的には理解できた感じです。面白い本の紹介ありがとうございました。