2012/08/06 00:00 | by Konan | コメント(1)
Vol.152: LIBOR
今回は、とても簡単に話題のLIBOR問題に触れます。最近とても有名になりましたが、London Inter Bank Offered Rateの略で、ロンドン市場での銀行間取引の際、資金の出し手がどの程度の金利を取り手に提示しているかを示す指標金利です。少数の大手銀行の数字に基づき計算されてきましたが、実態と異なる金利が報告されていたことが発覚し、関与したトレーダーの刑事責任、関係銀行の損害賠償責任、そして監督当局や中央銀行、特に英国の中央銀行であるBank of England (BOE)のタッカー副総裁の責任問題に発展しています。
LIBORは様々な取引、例えば貸出取引や金利スワップ取引の際参照され、基準とされる重要な金利なので、それが歪んでいたとすればとても大事というのが、大方の受け止め方と思います。実際、この歪みをきちんとそして予め理解出来たとすれば、大儲けする良い機会になると思いますし、例えば貸出基準金利が実際の銀行の調達金利水準に比べ高く設定されていたとすれば、借り手にとり大きな損失です。
他方、今回特に注目されているのは、金融危機時にインターバンク市場の機能が不全となり、高い金利を提示しても資金の出し手がみつからないような状況下、それを素直に開示してしまうと、大手銀行の信用不安問題に発展し、金融危機が一段と深刻化しかねないため、実態より低い金利を報告していたという問題です。見方によっては、例えば市場調達金利の実情より低目の金利水準に貸出金利を設定していたことにもなる訳で、こうした行動に同情してしまう思いも持ちます。
むしろ興味があるのは、今後LIBORがどうなっていくかです。今回これだけ話題を集めるのは、LIBORの影響力が大きいからですが、逆に言えば、今回の件を契機にLIBORが無くなってしまうとすれば、大変な事態です。多くの取引が指標を失い、消滅してしまう恐れも杞憂ではありません。
従って、何としてでもLIBORを存続させる、ただし、その算出過程の透明性や正確性を向上させる方向しか解は無いように思います。例えば、対象銀行数を拡大する、算出過程に厳しいチェックを入れるなどの方向です。海外の報道を聞いて感じたことは、古き良き時代を引き摺るロンドン市場における、金融機関と中銀・監督当局の間のぬるま湯的な関係への批判の強さです。そして、そうした批判の渦中で、とくに風当たりが強いBOEに、FSA(日本の金融庁に当たります)が近々吸収されることが既に決定されていることは、皮肉な状況とも思えます。結局、今回の教訓は、金融機関と中銀・監督当局の関係は厳格でなければならないという、とても当たり前のことに帰結するのでしょうか。
当社に無断で複製または転送することは、著作権の侵害にあたります。民法の損害賠償責任に問われ、著作権法第119条により罰せられますのでご注意ください。
One comment on “Vol.152: LIBOR”
コメントを書く
いただいたコメントは、チェックしたのち公開されますので、すぐには表示されません。
ご了承のうえ、ご利用ください。
![The Gucci Post [世界情勢・政治・経済金融 × プロフェッショナル]](https://guccipost.co.jp/blog/konan/wp-content/themes/gucci_blog/images/etc/head_logo_20220126.png)

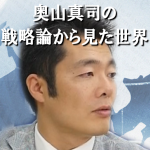



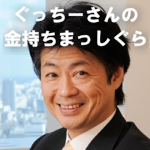


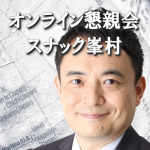

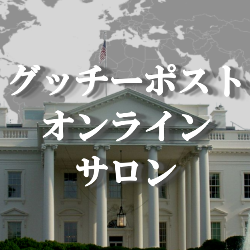



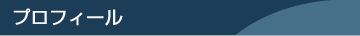


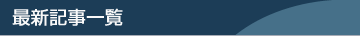

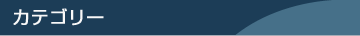
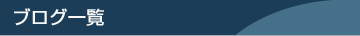
バレタのは・・
断腸の思い・・
しかし・・
絶好の狩場は・・手放せない・・
密猟・・死刑でも・・無くならなかった・・・