2011/11/07 00:00 | by Konan | コメント(1)
Vol.113: 日銀展望レポート
今回は、先月27日に公表された日銀の展望レポートを取り上げます。このコーナーで展望レポートを紹介するのも、もう5回目でしょうか。このレポートは、年2回、4月末と10月末に公表される日銀の最も重要なレポートで、先々の経済や物価の見通しと、金融政策運営の基本方針が語られます。また、具体的な数字の形で実質経済成長率および物価上昇率の見通しも示されるので、その点では分かりやすい内容です。
このレポートは、まず「もっとも蓋然性が高いとみられる見通し」を示し、次に「それは外れるかもしれない。外れるとすればどのような要因によるものか」という見通しの不確実性を示し、そして最後に金融政策運営方針を示すという構造になっています。
蓋然性が高い見通しについては、文章的には結構強気な表現になっています。具体的には「わが国経済は、当面、海外経済減速や円高の影響を受けるものの、見通し期間(2013年度まで)を通じてみれば、新興国・資源国を中心に海外経済が高めの成長を維持するとみられることや、震災復興関連の需要が徐々に顕在化していくことなどから、緩やかな回復経路に復していくと考えられる」としています。そして、「日本経済は、「中長期的な物価安定の理解」(消費者物価指数の前年比+1%程度)に基づいて物価の安定が展望できる情勢になったと判断されるにはなお時間を要するものの、やや長い目でみれば、物価安定のもとでの持続的成長経路に復していくと考えられる」とします。
ただ、政策委員会メンバーの見通しを数字でみると、実質経済成長率については、3か月前(7月)時点で2012年度+2.9%だった予想が今回は+2.2%と下方修正されており、2013年度は+1.5%と、2012年度対比成長率が下がる見通しです。物価(消費者物価)についても、来年度+0.1%上昇と、7月時点見通し(+0.7%)対比下方修正です。要は文章表現で読み取れるイメージに比べ、数字は弱気と読むこともできます。
次に、この見通しがはずれるかもしれない蓋然性(より長期的な視点も踏まえつつ、金融政策運営の観点から重視すべきリスク)については、「バランスシート調整が米国経済に与える影響」「欧州のソブリン問題について、今後、財政と金融システム、実体経済の負の相乗作用が、強まっていくことにならないかどうか」「新興国・資源国で、物価安定と成長を両立することができるかどうか」「こうした海外情勢を巡る不確実性や、それらに端を発する為替・金融資本市場の変動が、わが国経済に与える影響」「国際商品市況の先行き(上下双方向に不確実性が大きい)」などが指摘されています。どれも大きな要因で、蓋然性が大きいとされた見通しが外れる可能性(しかも下の方に外れる可能性)には十分注意しておく方がよさそうです。
そして金融政策運営については、「日本経済がデフレから脱却し、物価安定のもとでの持続的成長経路に復帰するために、包括的な金融緩和政策を通じた強力な金融緩和の推進、金融市場の安定確保、成長基盤の強化の支援という3つの措置を通じて、中央銀行としての貢献を粘り強く続けていく」との方針を示しています。
紹介は以上です。米国や欧州情勢、あるいは新興国のリスクなど、もう少し踏み込んだ分析が欲しかった印象ですが、いかがでしょうか?なお、それはそれとして、このレポートの良さは様々なグラフが掲載されていることです。お時間があるとき、是非図表を眺めてみられることをお勧めします。
当社に無断で複製または転送することは、著作権の侵害にあたります。民法の損害賠償責任に問われ、著作権法第119条により罰せられますのでご注意ください。
One comment on “Vol.113: 日銀展望レポート”
コメントを書く
いただいたコメントは、チェックしたのち公開されますので、すぐには表示されません。
ご了承のうえ、ご利用ください。
![The Gucci Post [世界情勢・政治・経済金融 × プロフェッショナル]](https://guccipost.co.jp/blog/konan/wp-content/themes/gucci_blog/images/etc/head_logo_20220126.png)
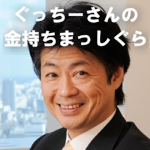

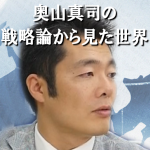



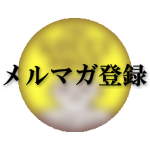
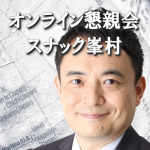


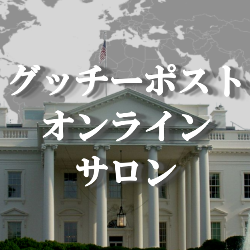



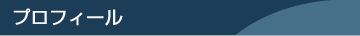



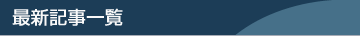

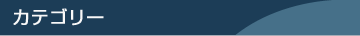
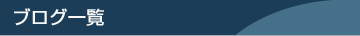






>>米国や欧州情勢、あるいは新興国のリスク
それは・・
部外秘のレポートがあるのでは・・・