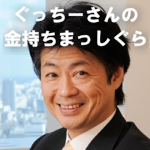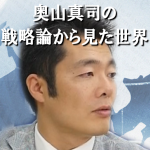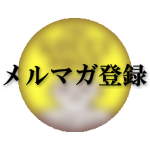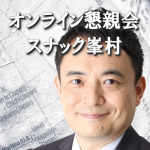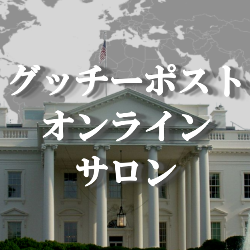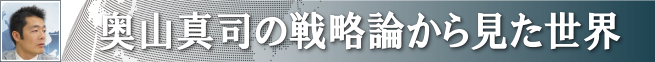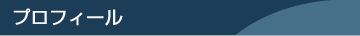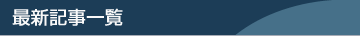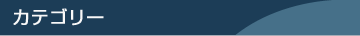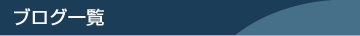2025/10/04 16:00 | 戦略論 | コメント(0)
プランBを考えるべき?
今週の戦略関連のニュースで注目すべきは、やはりアメリカのヘグセス国防長官が現地時間の9月30日に、ワシントンDC近郊のクワンティコ海兵隊基地に世界中から800人以上の将軍たちを一斉に集めて演説し、自らの政策を雄弁に語ったことでしょうか。
■ 「太った将軍は容認できない」と言い放ったヘグセス氏 危ぶまれる日米「ワンチーム」の崩壊(10/1 Forbes)
これについては米軍の元軍人などを中心に、すでに様々な意見が出ています。CNNなどのリベラル系のメディアでは批判的な人々の意見が集められた一方、FOXのようなメディアでは絶賛とまでは言わないまでも、かなり好意的な意見が目立ったのが印象的です。
私からすると、この40分にわたるヘグセスの演説の多くの部分は、異様に既視感のあるものでした。というのも、本メルマガ第3号と第11号(以下のリンク参照)で取り上げていたとおり、とりわけ彼の「戦士」という、今回の演説の核心にある考え方については、すでに彼の著作の中で繰り返し述べられていたことだったからです。
・「次期トランプ政権の爆弾人事」(24/11/21)
・「ヘグセス国防長官候補と『戦士の文化』」(1/18)
もっとも、私が見ている限りでは、今回の彼の演説そのものは、とりわけ戦闘に従事する軍種や部隊の兵士たちにとっては当然のものと言えるものばかりであり、おそらくメディアで言われているほど米軍内の分断を引き起こすようなものではありません。
実際、リベラルなはずのMSNBCの番組では、元陸軍将官で外交官まで務めたマーク・キミットが、思った以上に中立的な意見を述べていました。
■【動画】Hegseth wants Pentagon to be ‘a frat’: Journalist(10/1 MSNBC)
それよりも私が問題だと感じたのは、その後のトランプ大統領の演説です。全体的に支離滅裂でしたが、特に気になったのは、「内なる敵」を倒すために、民主党系の力が強いシカゴのような大都市に、米軍(州兵)を派遣する方針を継続すると表明したことです。
■ トランプ氏、アメリカの都市を「軍の訓練場」にすべきと 将官らに演説(10/1 BBC)
すでに何度か述べておりますが、アメリカの大統領が目指すものとして基本的に求められているのは、米国の「団結」であり、決して「分断」ではないはずです。しかし危険なことに、今の大統領は、自身の政治的な言論だけでなく、実力部隊である米軍を国内に派遣するという実際の行動まで示唆しており、まるで内戦を煽っているかのようです。
ここで参考になるのは、今年の1月にフォーリン・アフェアーズ誌に掲載された、ミネソタ大学のロナルド・クレブス教授による論考です。タイトルはズバリ「トランプ vs 米軍」というものです。
■ Ronald R. Krebs『Trump vs. the Military』
政府と軍の関係、つまり「政軍関係」などを専門とするクレブス教授は、まず一般的な話として、ポピュリスト政権は、しばしば軍を賛美し、戦死者や歴史的勝利を国家の象徴として利用するが、やがて独立性を持つ軍を脅威と見なし、粛清や制度改編に転じると説きます。
その例として、インド、トルコ、ハンガリーなどでの事例を挙げつつ、実際に多数の将兵解任や昇進制度の改変が行われたことを説明します。
トランプ政権についても、たとえば第一期の2017年には「自分の将軍たち」を閣僚に迎えたが、忠誠を欠くと見なして即座に更迭したことや、警察による黒人のジョージ・フロイド殺害に対する抗議デモや、アフガニスタン撤退などを契機に軍への批判を強め、軍幹部を「戦争を望む軍需企業の傀儡」と糾弾したこと、戦死者を侮辱したとの報道も出たことなどを指摘します。
結論としてクレブス教授は、これらの歴史的事例に鑑みれば、軍の自律性と専門性を守ることこそが国家安全保障の基盤につながると断言。トランプ第2期政権がこの教訓を無視すれば、米国の軍事力と民主政治は共に重大な危機に直面するだろうと警告しています。
つまり、トランプ政権の米軍の雑で強権的な使い方はかなり問題という話なのですが、最近になって、同じくフォーリン・アフェアーズ誌に、この話とつながる形の論考が出ました。まるでホラーのような話なのですが、我々が真剣に考えなければいけない内容が含まれていますので、今回取り上げます。
※ここからはメルマガでの解説になります。目次は以下の通りです。
***********
プランBを考えるべき?
***********
▼「アメリカ後」の世界を
▼米国が敵に?
▼日本にとっての示唆
***********
近況報告
***********
いよいよ大学院で後期の授業が始まりました。来年の1月まで授業は続きます。
今期は昨年度とは劇的にスタイルを変えて、なんと「期末テスト」を実施することに(これまでは最後にレポート提出)。
その最大の理由は、やはり学生たちのChatGPTのような生成AIのレポートでの使用を制限したいからです。
去年まではそこまでAIを使用している例はほとんど見受けられなかったのですが、今年の前期の講義では、やたらとそれを使って発表資料を作っている例が見られ、学生たちにとってはほとんど学びになっていないと実感しました。
そのため、後期の最後ではなんと筆記試験を復活させることにしたのです。
これを発表した時、学生たちは実に微妙な顔をしていましたが、私も留学中には最後のシメとして筆記試験を経験しております。
日本語で書くのだから楽勝でしょ!というのが私の議論です。異論は認めません。
***********
好評発売中の書籍
***********
■『世界最強の地政学』文春新書
■『新しい戦争の時代の戦略的思考』飛鳥新社
■『サクッとわかる ビジネス教養 新地政学』新星出版社、改訂版(再び増刷決定!)
■『やさしくわかるエネルギー地政学』小野﨑 正樹、技術評論社
■『クラウゼヴィッツ: 『戦争論』の思想』マイケル・ハワード著、勁草書房
■『地政学:地理と戦略』コリン・グレイ&ジェフリー・スローン編著、五月書房新社
■『戦争の未来』ローレンス・フリードマン著、中央公論新社
■『インド太平洋戦略の地政学』ローリー・メドカーフ著、芙蓉書房出版、
■『戦争はなくせるか』クリストファー・コーカー著、勁草書房
■『デンジャー・ゾーン』マイケル・ベックリー&ハル・ブランズ著、飛鳥新社
■『スパイと嘘』アレックス・ジョスキ著、飛鳥新社
■『アジア・ファースト』エルブリッジ・コルビー著、文春新書(第三刷決定!)
■『認知戦:悪意のSNS戦略』イタイ・ヨナト著、文春新書(★最新刊★)
当社に無断で複製または転送することは、著作権の侵害にあたります。民法の損害賠償責任に問われ、著作権法第119条により罰せられますのでご注意ください。
いただいたコメントは、チェックしたのち公開されますので、すぐには表示されません。
ご了承のうえ、ご利用ください。
![The Gucci Post [世界情勢・政治・経済金融 × プロフェッショナル]](https://guccipost.co.jp/blog/mokuyama/wp-content/themes/gucci_blog/images/etc/head_logo_20220126.png)