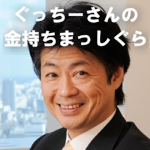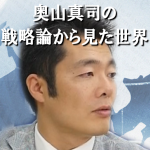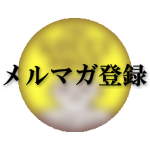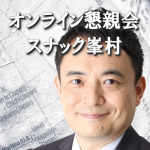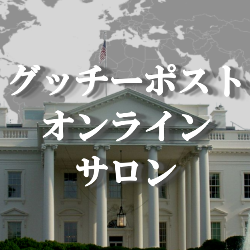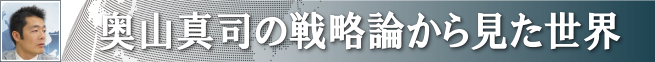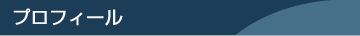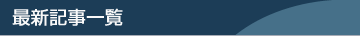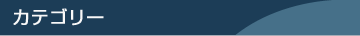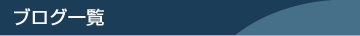2025/09/08 13:00 | 戦略論 | コメント(0)
アメリカが特殊部隊を北朝鮮に侵入?
先週の戦略関連のニュースで注目すべきは、なんといってもNYタイムズ紙のこのスクープですね。
■ How a Top Secret SEAL Team 6 Mission Into North Korea Fell Apart(9/5 The New York Times)
2019年1月に米海軍の特殊部隊が闇夜に紛れて原潜から潜水艇に乗り換えて北朝鮮に上陸し、通信傍受のための機器を設置しようとしたが、北朝鮮側の漁民のものと見られる船に見つかったので、射殺して任務を中止して撤退したというものです。
この作戦の様子を説明している箇所を訳してみました。
===
作戦のために米軍はSEALSの「チーム6」の「レッド中隊」を選んだ——オサマ・ビンラディンを殺害したのと同じ部隊である。SEALSの隊員たちは数か月間訓練を重ね、あらゆる動きが完璧でなければならないことを認識していた。
しかしその夜、黒いウェットスーツと暗視ゴーグルを装着し、無人と思われた海岸に到達したとき、作戦は瞬く間に崩壊した。
暗闇から北朝鮮のボートが現れた。船首の懐中電灯が水面を照らし出した。発見されると恐れた隊員は発砲した。瞬く間に北朝鮮船の乗員全員が死亡した。SEAL隊員は盗聴器を設置せずに海へ撤退した。
===
もちろんこの作戦は米国内の正式な手順を踏んだものではなく(連邦議員の何人かに知らせなければならない)、違法とされる可能性がかなり高いわけですが、驚くのはこれをトランプ政権の第一期の北朝鮮との核に関する交渉中に行っていたということですね。
記事にもあるように、トランプ大統領はその任務の重大さから作戦を直接承認したとされており、米朝双方ともこの話に関しては何も語っていないとしています。
このスクープ記事は、匿名ながら、現役・元軍人、元政府関係者など20数名(two dozens)に話を聞いて完成させたとのことです。
この記事で興味深かった点はいくつかあるのですが、一部を取り上げると、実はアメリカの特殊部隊はブッシュ(息子)政権下の2005年にも北朝鮮に上陸していたことや、オサマ・ビンラディンを殺害したあの「チーム6」の「レッド中隊」(DEVGRUとも呼ばれる)も、過去には何度も失敗していると指摘されていることです。
このように特筆すべき内容の記事ですが、今回はこの話をネタにしつつ、戦略論における特殊部隊について、私独自の視点から、重要と思われるポイントをお伝えしたいと思います。
※ここからはメルマガでの解説になります。目次は以下の通りです。
***********
アメリカが特殊部隊を北朝鮮に侵入?
***********
▼特殊部隊ってすごいの?
▼嫌われ者?
▼謎に包まれている?
▼諸刃の剣
▼戦略的な特殊部隊?
***********
近況報告
***********
少々怖い話を。
大阪に行ってまいりました。理由は講演を依頼されたから、なのですが、なんと依頼主が不明。
スケジュール帳にバッチリ予定が入れてあったので、おそらく誰かが確実に依頼してきたのは確かなのですが、過去のメールを検索しても、誰かに依頼されたような形跡はありません。
「お前が確認しなかったのがいけないのだろう」
と言われればそれまでなのですが、当日になって「先生、今日会場にいらっしゃるのですよね?」と言われても怖いので、とにかく大阪に行って一泊してきました。
幸いなことに(?)誰からも連絡はなく、しかしこちらも何本か締め切りの原稿があったので、大阪の町を楽しむことなくホテルにこもりっきりで仕事することになってしまったのですが・・・・
以上、真夏の怪談のような話でした。
***********
好評発売中の書籍
***********
■『世界最強の地政学』文春新書
■『新しい戦争の時代の戦略的思考』飛鳥新社
■『サクッとわかる ビジネス教養 新地政学』新星出版社、改訂版(再び増刷決定!)
■『やさしくわかるエネルギー地政学』小野﨑 正樹、技術評論社
■『クラウゼヴィッツ: 『戦争論』の思想』マイケル・ハワード著、勁草書房
■『地政学:地理と戦略』コリン・グレイ&ジェフリー・スローン編著、五月書房新社
■『戦争の未来』ローレンス・フリードマン著、中央公論新社
■『インド太平洋戦略の地政学』ローリー・メドカーフ著、芙蓉書房出版、
■『戦争はなくせるか』クリストファー・コーカー著、勁草書房
■『デンジャー・ゾーン』マイケル・ベックリー&ハル・ブランズ著、飛鳥新社
■『スパイと嘘』アレックス・ジョスキ著、飛鳥新社
■『アジア・ファースト』エルブリッジ・コルビー著、文春新書(第三刷決定!)
■『認知戦:悪意のSNS戦略』イタイ・ヨナト著、文春新書(★最新刊★)
当社に無断で複製または転送することは、著作権の侵害にあたります。民法の損害賠償責任に問われ、著作権法第119条により罰せられますのでご注意ください。
いただいたコメントは、チェックしたのち公開されますので、すぐには表示されません。
ご了承のうえ、ご利用ください。
![The Gucci Post [世界情勢・政治・経済金融 × プロフェッショナル]](https://guccipost.co.jp/blog/mokuyama/wp-content/themes/gucci_blog/images/etc/head_logo_20220126.png)